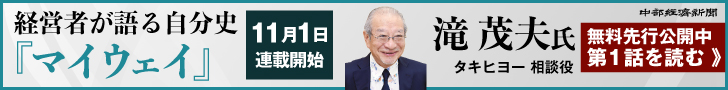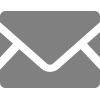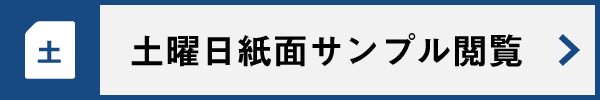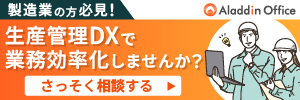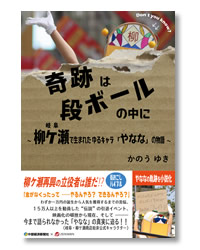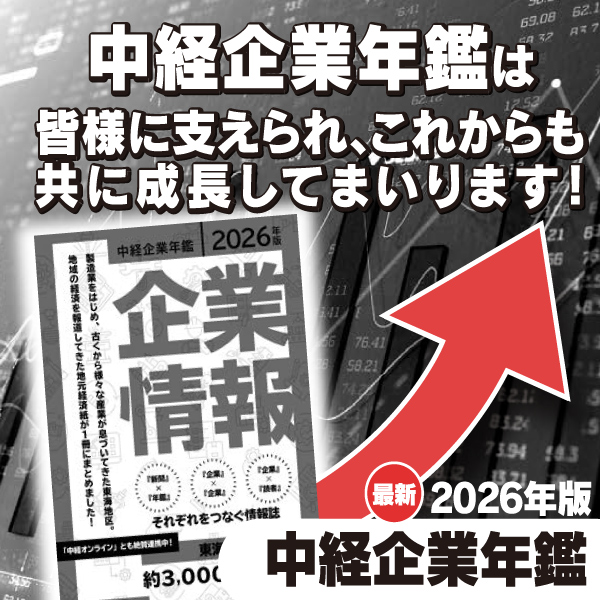新たなビジネスモデルを構築
浜木綿
代表取締役社長 林 永芳(はやし・ながよし)氏
小商圏店舗、M&Aも視野
①足元の状況は
2025年7月期は3月までの8カ月の全店売上高が前年と比べ5・7%増、既存店売上高も2・3%増だった。原材料価格や人件費などのコスト上昇に伴う値上げの実施で客単価が伸びたのが大きい。主力業態「浜木綿」は全店が8・0%増、既存店が4・2%増。宴会需要が回復し、既存店客数も99・3%と前年並みで推移している。
ただ、コスト増で利益を確保しにくくなっている。米、野菜、卵の価格上昇が著しい。人件費も尋常でないぐらい上がっている。何度か値上げしたが、コストの上がり具合に追いつかないのが実情だ。これからもコストが下がることは考えにくい。そういう世の中になったと割り切って乗り越えていくしかない。当社は国産米を使用しているが、26年7月期以降も国産米不足が続けば、外国産米の活用を検討する。
今後も値上げが避けられない。重要なのは値上げに見合った価値を提供することだ。浜木綿業態は基本サービスとおいしさに磨きをかけていく。
②現在の強化・重点事業は
今、最優先で取り組んでいるのが浜木綿業態の新しいビジネスモデルの確立だ。人手不足が続いており、新モデルは生産性向上がテーマになる。まずは料理人不足に対応し、調理現場にロボットを導入したいと考えている。すでに揚げ物や中華鍋を使う料理をロボットに置き換える研究を始めている。
また、ホールスタッフ不足対策として、人工知能(AI)の活用を模索している。浜木綿業態はメニューが豊富で、お客さまから料理の内容などを問われることが多々ある。スタッフ不足では接客に支障が出かねないため、料理の味や量の多少、アレルギー対応などお客さまのメニュー選びをAIで手助けできないかと思案している。活用できれば、顧客満足度の向上にもつながる。導入費用が高額だが、実用化に向けてしっかりと吟味したい。
人口減少でこの先、働き手はさらに減る。従来のビジネスモデルでは将来が見えてこない。ロボットやAIを駆使した新しいモデルをつくり上げ、次の時代につなげていく。
③今後の成長戦略は
浜木綿業態の新モデルを確立できた段階で新規出店に力を入れていく。これまで15~20万人商圏を出店条件としていたが、今後は10万人規模の小商圏にも踏み込んでいく。小商圏に適した小型店舗を開発し、出店拡大をねらう。
後継者不在の中華料理店の承継も視野に入れる。M&A(買収・合併)は過去に経験がないが、後継者不在店の承継は出店コストを抑えられる。設備やお客さまを引き継ぐこともでき、メリットが大きい。また、従来は郊外を出店地としていたが、中長期的には都心にも進出したい。今後、都心に見合った高価格業態の開発を本格的に検討する。
当社は中華料理の一本足経営だが、これからもそのスタンスに変わりはない。これまでに培った中華料理のノウハウ、システムを生かし、新しいことに挑戦して持続的な成長を目指していく。