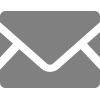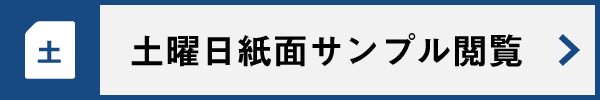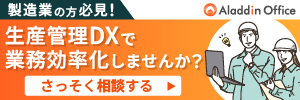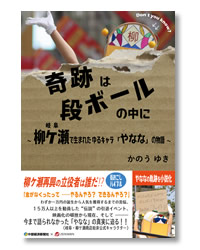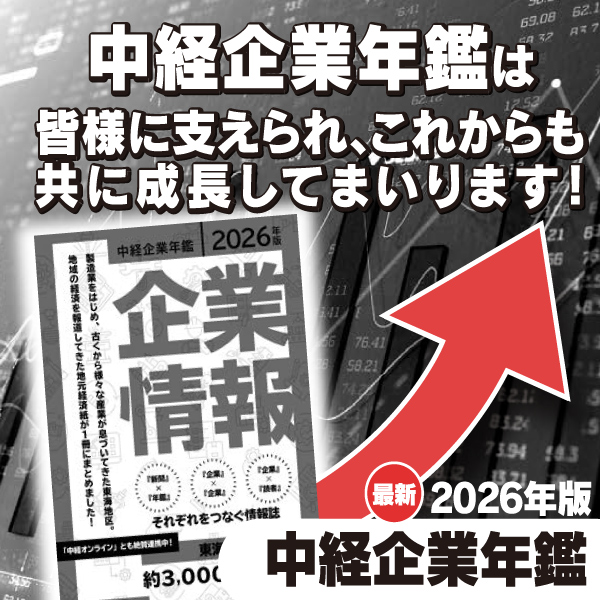環境特集
宇宙から温室効果ガスを監視「いぶき」
地球を見守る衛星
気候変動対策の要である温室効果ガスの排出量。その正確な把握は、各国の削減目標(NDC)やカーボン・クレジットの信頼性を支える根幹である。これを宇宙から監視しようという先駆的な試みが、日本発の「いぶき(GOSAT)」プロジェクトだ。環境省、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の3者が共同で進めるこの衛星観測計画は、温室効果ガスの〝見える化〟を実現した世界初の挑戦として国際的にも高い評価を受けている。
初号機「いぶき(GOSAT)」は2009年に打ち上げられた。世界中の大気中に含まれる二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)の濃度を、衛星から高精度で観測する能力を持つ。従来の地上観測では把握が困難だった森林や海上といった広大なエリアも含め、グローバルなモニタリングが可能となったことで、排出源や吸収源の分析に新たな視点が加わった。
この流れを受けて、2018年には観測能力を強化した2号機「いぶき2号(GOSAT-2)」が軌道投入された。観測対象はより細分化され、都市部や産業地域の排出動向も詳細に捉えることが可能となった。また、温室効果ガスに加え、大気汚染物質との相関分析も進められ、気候変動と人間活動の因果関係を明らかにする取り組みも強化されている。
3号機打ち上げへ
そして2025年6月24日、シリーズ3機目となる「GOSAT-GW」が打ち上げられる予定になっている。今回の特徴は、温室効果ガス観測に加えて「気象観測機能」を備える点にある。大気中の水蒸気や雲の分布、降水状況といった気象関連データを同時取得することで、温室効果ガスの移動メカニズムや気候モデルの精緻化が可能となる。地球全体の炭素循環と気象変動の相互関係を、より包括的に理解するための「複眼的観測」が本格的に始まる。
こうした宇宙ベースの観測インフラの整備は、経済活動における「カーボンニュートラル化の実効性」を裏付けるうえでも重要な役割を果たしている。たとえば、企業による温室効果ガスの自主的な削減努力や、国際的なカーボン・クレジット市場における取引の信頼性を高めるうえで、客観的なデータによる裏付けは欠かせない。GOSATのデータは、すでに世界各国の科学機関や政策決定者に活用されており、「国際標準」としての地位を築きつつある。
また、気候関連財務情報開示(TCFD)や自然関連財務情報開示(TNFD)といった枠組みの下で、企業が自らの炭素リスクや環境フットプリントを可視化し、投資家に対して説明責任を果たすことが求められている。衛星観測による正確な環境データは、こうした情報開示の精度を高め、サステナブルな資本市場の形成にも資する。
さらに注目すべきは、「いぶき」が単なる科学プロジェクトではなく、日本の宇宙産業・環境政策・データ経済の結節点としても機能している点である。衛星の設計・製造には国内メーカーの高い技術が投入されており、得られたデータはAI解析や地理情報システム(GIS)などと組み合わされて新たな民間サービスの創出にもつながっている。すでに複数のスタートアップや気候テック企業がGOSAT由来の情報をもとに再エネ導入支援や森林吸収量の推計サービスを提供している。
経済活動の新指標
「空から地球を診る」という視点は、今や地球規模の気候リスクと経済活動の健全性を同時に測定する〝新たな指標〟となりつつある。温室効果ガスの排出源や吸収源は、国家境界線ではなく、産業構造や土地利用と深く結びついている。だからこそ、グローバルな視野で、しかも科学的裏付けのある情報インフラが不可欠となる。
間もなく飛び立つGOSAT-GWは、日本が長年培ってきた宇宙・環境両分野の叡智を結集した存在である。国際社会の脱炭素競争が激化するなかで、その軌道上からのまなざしは、地球の未来だけでなく、経済の持続可能性そのものをも映し出すことになるだろう。