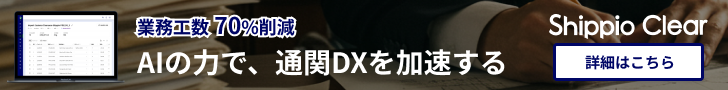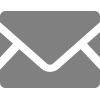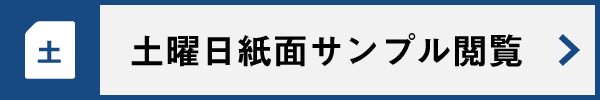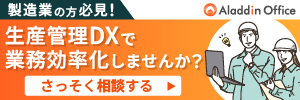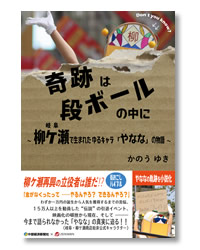環境特集
次世代エネルギーとして大きな可能性を秘めるアンモニア
今後5年間の世界平均気温過去最高になる可能性98%
脱炭素化に向けて多様な取り組みを進めているエネルギー分野でアンモニアに注目が集まっている。「刺激臭のある有毒物質」というイメージが強いが、日本はそのアンモニアの技術で世界をリードしている。
アンモニアの用途は世界全体でみると、その8割が肥料として消費されている。残り2割ほどは工業用で、メラミン樹脂や合成繊維のナイロンなどの原料となる。世界の人口は増え続けているため、食料確保の必要性から考えても、農産物の肥料として利用されるアンモニアの重要性は今後も変わらないと考えられている。
こうした底堅いニーズを背景に、世界各地の化学工場でアンモニアが生産されている。アンモニアを合成するには水素が必要で、その水素は主に天然ガスなど化石燃料由来のものが使われる。最近は、太陽光など再生可能エネルギー由来の電気で、水を分解してつくる方法も研究されているが、いずれにしても安全に運搬する技術は確立されており、陸上ではパイプラインやタンクローリーで、海上輸送にはタンカーが用いられる。安全性に対するガイドラインも整備されている。
石炭からアンモニアへ転換世界初の大規模実証実験
アンモニアがエネルギー分野で注目される理由は主に2つ。まず、次世代エネルギーである水素のキャリア、つまり輸送媒体として役立つ可能性を秘めているからだ。水素は常温常圧だと気体であるため、貯蔵・運搬するためには超低温で液化、超高圧で圧縮するという工程が必要となり、取り扱いが難しいという問題がある。そこで輸送技術が確立しているアンモニアに変換して輸送し、利用する場所で水素に戻すという手法が研究されている。
もうひとつの理由は、アンモニアの燃料化だ。アンモニアの分子式はNH³。水素(H)と窒素(N)で構成されていることからも分かるように、燃やしてもCO²を排出しない。こうした特性を踏まえた技術開発で特に期待されているのが、石炭火力発電のボイラーにアンモニアを混ぜて燃焼させる「火力混焼」である。その実証実験が今年、世界に先駆けて愛知県碧南市の発電所で始まった。
実証実験を行うのは東京電力と中部電力が出資する発電事業者JERAの碧南火力発電所4号機。100万kW級の設備を改造し、燃料の20%をアンモニアにし、安定して燃焼できるかや、有害な窒素酸化物の排出を抑制できるかなどを確認する。JERAは、早ければ2027年度にアンモニア混焼を商用運転に切り替え、2030年代に混焼率50%の本格運用、2040年代にアンモニア100%燃焼(専焼)の計画を描いている。
アンモニア燃料の活用で課題となるのは、アンモニアの安定的な量の確保だ。国内すべての石炭火力で20%混焼を行うために必要なアンモニアの量は約2000万トン。これは現在、世界の輸出入量にあたる。今後、混焼を実施する石炭火力発電が増えたり、混焼率が高まったり、専焼が始まったりすることによって、発電分野でのアンモニア利用が増えると、現在の生産量では足りなくなる。供給が不足すれば価格が高騰し、肥料の市場にも影響を与える。こうした事態を避けるための取り組みとともにサプライチェーンの構築が進めば、日本は世界の燃料アンモニア市場をリードできるのではないだろうか。