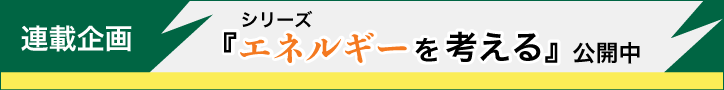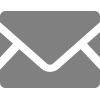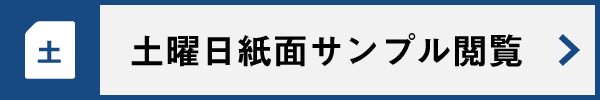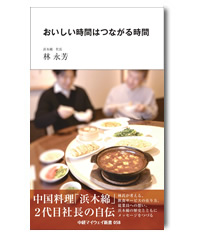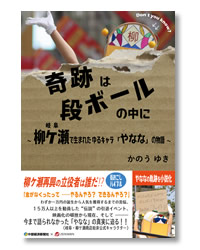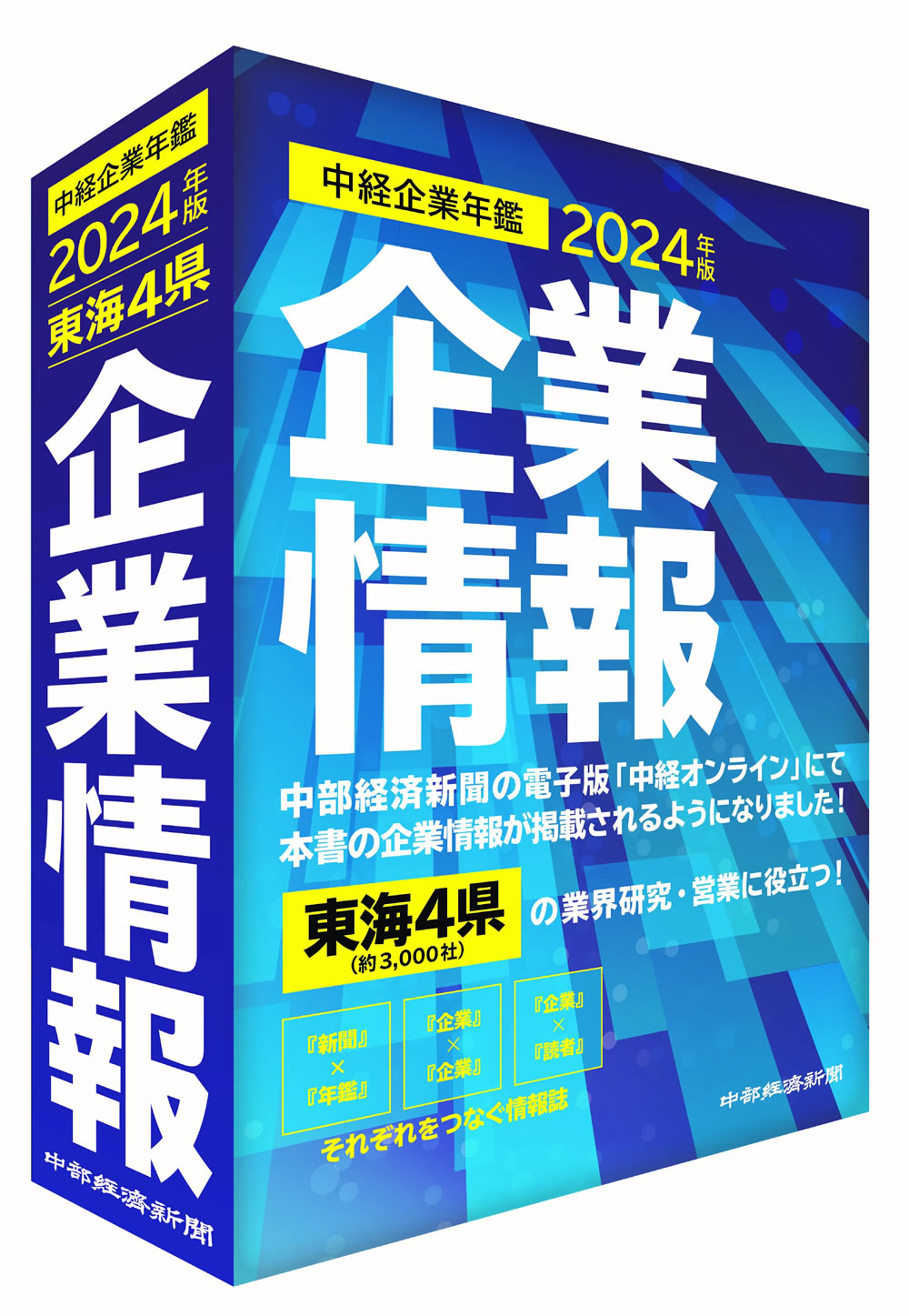環境特集
日本のグリーン成長戦略の鍵を握る再エネの切り札、洋上風力
秋田県沖で商業用運転開始
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて日本政府が策定したグリーン成長戦略は「経済と環境の好循環」を進める産業政策だ。そのなかでも化石燃料に頼ってきたエネルギーの改革は大きな柱のひとつ。例えば乗用車は2030年代半ばまでに新車販売で電動車100%にすることを目指しているが、そのような電化推進によって電力需要は最大50%増えると見込まれおり、電源の脱炭素化が急務となっている。そこでCO₂を出さない再エネを主力電源とし、2050年まで電力全体の50~60%、現状の3倍に引き上げる方針を打ち出している。
エネルギー改革の切り札と位置づけられたのが洋上風力発電だ。本格的な商業用運転は昨年に秋田県沖で始まってばかりだが、計画では設備容量を2040年までに3000万~4500万㌔㍗に増やす。これは大型の火力発電所に換算すると30~45基分に相当し、再エネ先進国ドイツの目標をも上回る。達成できるのか疑問の声も上がるが、それぐらいやらなければ2050年カーボンニュートラルは無理ということだ。
先行して進むヨーロッパと比べると日本は遠浅の海が少ないため、大量に導入するには、風車の土台を海底に固定する「着床式」だけでなく、海に浮かべる「浮体式」の技術開発が求められる。漁業者ら地域の同意も欠かせない。
産業化を図るための技術開発と人材育成
洋上風車のブレード(羽根)は長いもので100㍍におよび、先端は時速250㌔㍍以上で回る。壊れない素材や構造が必要で、そのレベルのものを製造するには高い技術を要する。現在、海外に頼っている状況だが、目標達成に向けては、部品を国内調達できるようにして、メンテナンスも対応できるよう産業化を図っていくことが不可欠とされている。そのためにも技術開発や人材育成に対する有効な対策を政府が継続して打ち出していけるかにかかっている。
再エネの牽引役だった太陽光は、大規模開発が難しくなりつつある。脱炭素と電力の安定供給に向けて、洋上風力に向けられた期待は今後一段と高まりそうだ。