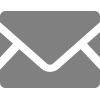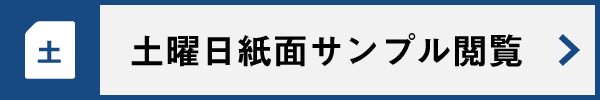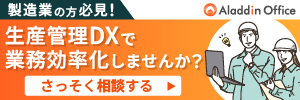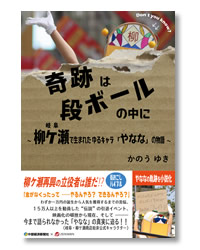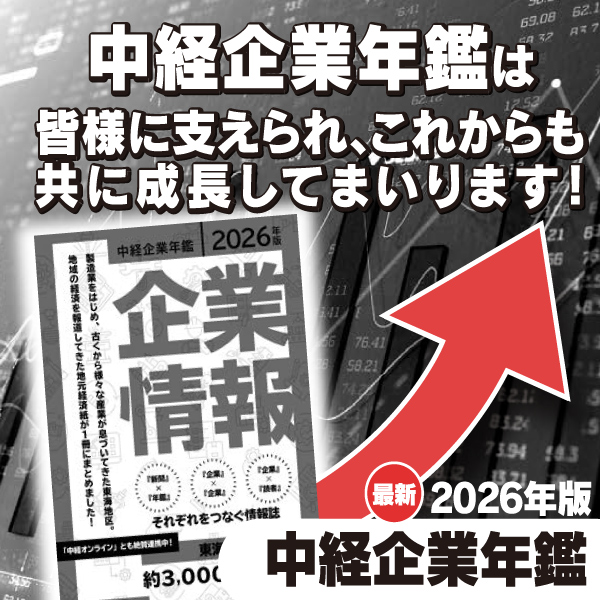電力システムは安定供給を大前提に
エネルギー経済社会研究所代表取締役 松尾 豪さん

まつお・ごう 学生起業への参画などを経て、2012年新電力のイーレックス入社。営業部、経営企画部に在籍。その後、アビームコンサルティング、ディー・エヌ・エーで国内外電力市場・制度の調査を担当、分散電源事業開発にも携わった。21年3月から現職。CIGRE(国際大電力システム会議)会員、電気学会正員、公益事業学会会員、エネルギー・資源学会会員。
電源構成の最適化重視を評価
――ウクライナ戦争や中東紛争の影響で化石燃料価格が高騰し、日本でも電気、ガス料金が高くなり、国民生活を苦しめています
「国内の電気、ガス料金が高くなった背景には、ウクライナ戦争などによる国際情勢の不安定化が招いた国際的な化石燃料価格の高騰に伴う輸入LNG(液化天然ガス)の価格上昇があります。これに対し、2025年後半から27年にかけて第二次トランプ政権下の米国とカタールで大規模なLNGプラントが相次ぎ稼働するため、当面は世界的な需給逼迫(ひっぱく)感が薄れ、国内の電気、ガス料金は、為替にもよりますが少し下がっていく方向にあると思います。しかし、中長期的には脱炭素の潮流の中で化石燃料価格には不確実性がつきまとい、再度の価格高騰も否定できません。やはり国内の電気、ガス料金を低く抑えるためには、エネルギー自給率を引き上げていく必要があり、再生可能エネルギーの拡大と原子力発電所の再稼働が非常に重要になります」
――再エネと原子力といえば、政府は脱炭素電源として両者の最大限の活用を柱とする40年度に向けたエネルギー基本計画(エネ基)を閣議決定しました。
「エネ基は脱炭素電源の確保について、『再エネか原子力か』という二項対立的な議論にせず、いずれも最大限活用することが不可欠としました。難しい調整があったことをうかがわせますが、おおむね評価できます。また、『特定の電源や燃料源に過度に依存しない』と明記し、エネルギーミックス(電源構成の最適化)が意識されており、脱炭素電源への移行期間に主力となるLNGの確保に向けた措置を盛り込んだことも評価できるポイントです。脱炭素の実現を促す移行燃料として国際的に認知されたLNGは、世界的な獲得競争が一段と激化することが見込まれています。日本のサプライヤーは他国とは異なり、都市ガスの販売や発電などLNGの最終需要を持っており、下流部門に強みがあります。こうした強みを生かして、石炭比率の高い東南アジア諸国など海外にも供給市場を広げ、国際市場で戦えるプレイヤー(企業)を育成していくことが重要です」
――再エネ、原子力、火力のバランスの取れた電源構成を実現していくうえでの課題は、どのようなことでしょうか。
「原子力については、原発の再稼働に加えて、将来的には新増設していくことも考えるべきです。50年のカーボンニュートラルを掲げている足元でデジタル化が急速に進展し、半導体工場やデータセンターの増加が見込まれています。これらの施設が24時間にわたって大量の安定した脱炭素の電気を求めても、再エネだけでは対応しきれません。データセンターと原子力の親和性が高いことは、米国でマイクロソフトやグーグルなどテック大手各社が原発活用に動いていることでも明らかで、日本でもこうした考え方が重要になります。再エネはできるだけ増やしていくべきですが、原発建設には長い年月を要するという時間軸の問題があり、短期的な電力需要増に再エネとLNG火力で対応していく役割もあります。このうちLNGはあくまでも脱炭素化への移行燃料ですから、中期的には新増設された原発に順次置き替えていく二段構えの戦略が必要だと考えています」
原発で供給安定化と料金抑制
――原子力については、日本では反原発感情が根強くあります。
「原発を再稼働している電力会社の料金は、家庭用で2割程度安くなっており、電気料金高騰下で原発の重要性への理解は広がっていると思います。また、日本には東日本大震災での福島第一原発事故を教訓として策定した、世界で最も厳しい原子力規制委員会の新規制基準があります。この新規制基準に則って再稼働を目指す原発に対し科学的な安全性評価を正しく行うことが重要ですが、最近の世論調査では、若年層を中心に原発再稼働に賛成する人が半数を超えて反対を上回る傾向にあり、新規制基準への評価が浸透してきていると思います。もう一つは、国や電力事業者が原発立地地域との連携を一段と強化していく必要があります。例えば、大容量の脱炭素電源を求める半導体工場やデータセンターなどの電力多消費型産業を原発の近くに誘致するなど地域経済の発展につなげるプランを国と事業者が一体となって進めていくという考え方も必要でしょう」
――経産省はエネ基と並行して、16年の電力小売り全面自由化で始まった電力システム改革の検証を進めており、25年4月以降に制度改正の議論に入る方針です。批判の多い現行システムの問題点はどこにあるとお考えですか。
「電力システム改革は、①安定供給の確保②電気料金の最大限抑制③需要家の選択肢拡大――の三点を目標に実施しましたが、このうち最も重要な安定供給についてしっかりと考慮された議論が尽くされたのかという点では、疑問が残ります。16年の電力小売り全面自由化、20年の発送電分離と制度改革への工程表が決まっていた中で、脱炭素の潮流など新たな要素も踏まえながら行われた議論では、全体のバランスに配慮した制度設計に至らなかったとも言えます。また、電力の安定供給が確保されなくなると電気料金の抑制が難しくなります。実際、21年1月の電力需給逼迫時には卸電力価格が通常の20倍以上に急騰し、新電力の市場価格連動メニューを契約していた家庭では月10万円近くの電気料金を請求されたケースもありました。さらに、電気料金高騰が続くとインフレを招き、部材や資材が高騰して再エネ導入にも足かせになります。その意味では、安定供給が確保できないと、経済効率性と環境適合性にも影響し、エネルギー政策の基本である3E(エネルギー安定供給、経済効率性、環境適合性)のすべてが崩れることになります」
――電力システム改革は安定供給重視に改めるべきということですか。
「ウクライナ戦争以降のエネルギー危機では、国民を含めて安定供給への課題を再認識しました。今後は安定供給を大前提とした制度設計に改めていく議論が必要だと思っています。ウクライナ戦争は想定外であったかも知れませんが、電力は国民生活を支える基盤であり、想定外は許されません。安定供給体制を維持・強化していくためには、電力小売り自由化市場に新規参入した新電力も大手電力と同様に発電事業者との間で電力調達の長期契約を結ぶなど、発電事業者の燃料確保の責任を担う仕組みも必要でしょう。かつて電気事業は『公益事業』とみなされており、自由化された今も国民の多くは電気料金を公共料金と思っています。国民が求める公益性の観点からも、電力システム改革は検証されるべきです」
――欧米の脱炭素政策に揺り戻しがあるといわれる中で、日本はエネルギー・脱炭素政策をどう進めていくべきでしょうか。
「私は日本のエネルギー・脱炭素政策を論じる中で、『現実的なトランジション(移行)のイノベーター(革新者)を目指せ』と申し上げています。野心的なトランジションを目指した欧米では、実際に脱炭素政策に揺り戻しが起きています。現実的なトランジションでないと、結果的に脱炭素が進まず、巡り巡って最後は国民生活に影響することになるのです。エネルギー政策は多岐にわたるため、何か特定の対策で脱炭素が達成できるのかといえば、そうではありません。その意味で、今現実的なトランジションの重要性が再認識されている中で、イノベーターを目指すのが、日本が取り得る最善の道だと考えています。具体的には、再エネにしっかりと投資してエネルギー自給率の向上に努めるとともに、電力供給の安定化と電気料金抑制に資する原発の再稼働と新増設を進めることが重要です。火力は短期的には維持・リプレース、中長期的にはアンモニア火力やCCS(CO2回収・貯蔵技術)の実用化などカーボンフリー化を着実に実行していかねばなりません。あれもこれも、幅広く対応していかなくてはいけないのが、日本の実情です」
2040年度エネルギー基本計画の電源構成
| 2023年度(速報値) | 2040年度(見通し) | ||
| エネルギー自給率 | 15.2% | 3~4割程度 | |
|---|---|---|---|
| 発電電力量 | 9854億キロワット時 | 1.1~1.2兆キロワット時 | |
| 電源構成 | 再エネ | 22.9% | 4~5割程度 |
| 太陽光 | 9.8% | 22~29%程度 | |
| 風力 | 1.1% | 4~8%程度 | |
| 水力 | 7.6% | 8~10%程度 | |
| 地熱 | 0.3% | 1~2%程度 | |
| バイオマス | 4.1% | 5~6%程度 | |
| 原子力 | 8.5% | 2割程度 | |
| 火力 | 68.6% | 3~4割程度 | |
| 2023年度(速報値) | 2040年度(見通し) | ||
| エネルギー自給率 | 15.2% | 3~4割程度 | |
|---|---|---|---|
| 発電電力量 | 9854億キロワット時 | 1.1~1.2兆キロワット時 | |
| 電源構成 | 再エネ | 22.9% | 4~5割程度 |
| 太陽光 | 9.8% | 22~29%程度 | |
| 風力 | 1.1% | 4~8%程度 | |
| 水力 | 7.6% | 8~10%程度 | |
| 地熱 | 0.3% | 1~2%程度 | |
| バイオマス | 4.1% | 5~6%程度 | |
| 原子力 | 8.5% | 2割程度 | |
| 火力 | 68.6% | 3~4割程度 | |