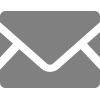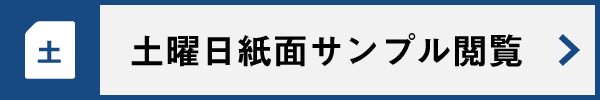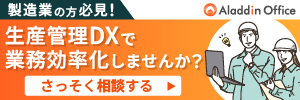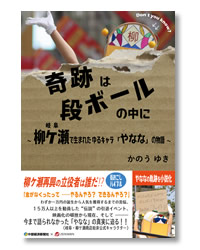思い切ったグリーン産業政策が肝心
タナカグローバルCEO、元国際エネルギー機関(IEA)事務局長 田中 伸男さん

たなか・のぶお 1950年神奈川県生まれ。72年東京大学経済学部卒。通産省(現経産省)入省、在米日本大使館公使、経済産業研究所副所長、通政局通商機構部長、経済協力機構(OECD)科学技術産業局長などを経て、2007年から4年間欧州出身者以外で初の国際エネルギー機関(IEA)事務局長を務めた。日本エネルギー経済研究所特別顧問、笹川平和財団会長などを経て現職。東京大学公共政策大学院客員教授。
GX戦略は正しい判断
――ロシアのウクライナ侵攻によって欧州は深刻なエネルギー危機に陥り、エネルギー安全保障の重要性が強く再認識されています。
「国際エネルギー機関(IEA)は今回の危機を『ファーストグローバルエナジークライシス』(初めての世界的なエネルギー危機)と言っています。石油だけでなく、あらゆる化石燃料資源が不足し、価格が高騰して世界中を危機に陥れています。戦争を起こしたロシアは化石燃料の世界最大の輸出国で、特に欧州は天然ガスを筆頭にロシアの化石燃料に多くを依存していました。そのロシアが天然ガスを武器に使いパイプラインを止めたわけですから、欧州のエネルギー事情は一変しました。欧州の中でもドイツは、天然ガスの約55%をロシアから調達していました。急速なロシア依存を進めたメルケル前首相の最大の誤りだと思います。そのドイツはLNG(液化天然ガス)設備の建設を急ピッチで進め、調達先の多様化に動き出しています。欧州全体では再生可能エネルギーに加速度的に資金を投じ、脱炭素とエネルギー安全保障の両方を強化しようとしています。フランスや英国が原子力発電所の新設計画を表明し、ベルギーが2025年閉鎖予定の原発2基の稼働延長を決定するなど原子力への前向きな姿勢が強まっているのも、ロシア依存から脱却し、脱炭素とエネルギー安保の両立を目指すためです」
「私はIEA事務局長時代の09年に当時のドイツ・メルケル首相に呼ばれてエネルギー問題を議論し、原子力について質問したことがあります。メルケル首相は『私は科学者で、原子力の重要性は理解している。私が原子力をやるには票を頂戴』と言いました。その後自民党との連立政権下で原子力を復活させましたが、11年の福島第一原発事故を受けて22年末での原発全廃を決定。今回の危機では政権を引き継いだショルツ首相は、残っていた原発3基の運転を延長し原発全廃を23年4月半ばまで延期しました。政治家が世論を忖度して政策をころころ変えるのは、時間軸の長いエネルギー政策にとっては致命的であり、エネルギー安保上も問題です」
――日本もエネルギー安保の強化に動き出しています。
「日本は岸田首相が昨年、脱炭素社会の実現に向けたグリーントランスフォーメーション(GX)戦略として、脱炭素電源である再エネと原子力の最大限の活用を打ち出し、安全が確認された既存原発の再稼働を急ぎ、運転期間も延長する方針を示しました。エネルギー安保上のリスクが高まっている中で非常に正しい判断だと思います。原発再稼働を進めれば、100万キロワット級1基あたりで年間約100万トンのLNGを節約できます。この余剰LNGを欧州やアジアの困っている国に回せば短期的な国際貢献につながるし、ロシア・サハリンからのLNG調達が仮に途絶えた場合でも、原発再稼働で影響を抑えることができます。ロシアリスクに備えるには、まずLNG消費を抑制する原発再稼働を急ぐ必要があり、万一を想定してさまざまな手を打っておくことがエネルギー安保の基本です」
エネルギー安保は希少金属へ
――今回の危機は脱炭素への流れの中で起きましたが、IEAは最近、「化石燃料の上流投資は不要」「化石燃料の需要ピークは20年代半ば」など衝撃的な内容の報告書を相次ぎ発表しています。
「21年5月に公表した報告書『ネットゼロ2050』では、各国政府が公表している脱炭素目標を達成するとの前提で『新規の石油・ガス上流投資は要らなくなる』と書きました。IEAは各国政府が目標達成したケースの話で、『こうしなさい』と言っているわけではないと説明しましたが、石油業界は大騒ぎになりました。石油ショックをきっかけに1974年に発足したIEAは、今度は石油業界に〝IEAショック〟を起こしたと言われました。さらに、昨年10月の『世界エネルギー見通し2022』では、『化石燃料需要は20年代半ばから減少に転じる』と化石燃料需要のピークを初めて示しました。石油もさることながら、まだ黄金期は続くと見られていた天然ガスも黄金期は終わりかけていると書いてきたのには本当に驚きました。しかし、最近は石油需要のピークはコロナ前の19年だったのではとの議論もあり、化石燃料の将来は短い期間しか残されていないと考えておいた方が良いし、世界はとんでもないスピードで動いています」
――欧米は巨額の補助金を投じるグリーンな産業政策を競っています。
「米国が昨年8月に成立させた『インフレ抑制法』は、約50兆円もの補助金を使って気候変動対策やエネルギー安全保障関連の産業育成を狙った産業政策です。1980年代後半に私がワシントンに赴任していたころは、半導体を中心に日本の産業政策は間違った政策だと米国からずいぶん非難されたものですが、今や環境・気候変動に対応するグリーンな産業政策は善であり、どんどん進めると言います。これに対し自由貿易の原則に反すると抗議したEU(欧州連合)も、脱ロシアの早期実現を目指す『リパワーEU』を策定し、再エネの大量導入や水素の社会実装に巨費を投じる計画をしています。日本は早く頭を切り替えて、欧米と同じような手法をとらないと間に合わないかもしれません。水素ではトヨタ自動車が14年に燃料電池車『ミライ』を発売するなど日本が先行しましたが、普及が進まず、社会実装に手間取っているうちに欧米に追い越されつつあり、もう一度リーダーシップを取り戻さなければいけません。今、火力発電最大手のJERA(ジェラ)が実用化に取り組んでいるアンモニア火力は、少し前までは石炭火力を維持する方便だろうと批判していたドイツも見方を変えており、世界中が注目しています。発電に使うとなれば、大量の需要が生まれます。早期にクリーンなアンモニア・水素の利用技術や製造、サプライチェーン構築に政府が支援して取り組まないと、世界に取り残されることになりかねません」
――日本にも思い切ったグリーン産業政策が必要ということですか。
「日本も新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に2兆円のグリーンイノベーション基金をつくりましたが、研究開発だけではだめで、実装するための思い切った補助金をつけないと産業界はついてきません。日本では供給サイドから脱炭素を見ていますが、実際の変化は需要サイドから来ています。米アップルでは、これからはグリーンな製品でなければ売れないため、部品サプライヤーは全部グリーンになってくださいと求めています。これは自動車でも同様で、欧米市場ではグリーンな電気自動車(EV)しか販売できなくなります。こうした動きに対応するには、再エネ、原子力、アンモニア・水素火力など電源の脱炭素化が不可欠で、それができないと産業はグリーンな電力を求めて海外に逃げてしまいます」
――脱炭素によってエネルギー安保の概念も変化すると言われています。
「IEAはエネルギー危機を機に脱炭素が加速する中で、エネルギー安保は大きく変わろうとしていると指摘。化石燃料を燃やす時代はそれを保有する国にパワーがあったが、これからはEVや電力貯蔵などに必要な蓄電池に使うコバルト、ニッケルなどのレアメタル(希少金属)や水素が重要な戦略物資になると見ています。エネルギー安保は石油備蓄から希少金属、水素の備蓄に代わるということです。現在の希少金属貿易が中国の独占に近い状態にあるというリスクを抱えているのは、環境汚染問題に対応できない先進国がコストを抑える意味もあって精錬を中国に押し付けてきた結果でもあります。日本はすでにベトナムやマレーシアからの調達を増やしているように調達先は多様化できる可能性があります。同時に、希少金属代替材料開発や希少金属に依存しない電池開発も進められており、イノベーションによっても新たなエネルギー安保上の懸念は払拭(ふっしょく)できると思います」