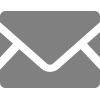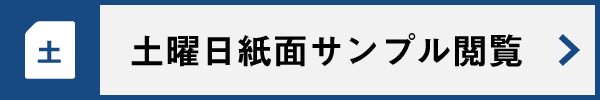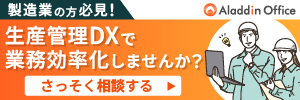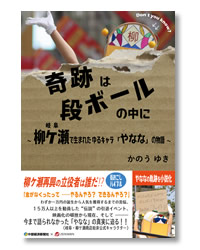希望ある脱炭素社会の未来図描くべき
NewsPicks(ニューズピックス)ニューヨーク支局長 森川 潤さん

もりかわ・じゅん 1981年米国ニューヨーク州生まれ。トロント大学留学、京都大学文学部卒。産経新聞を経て、週刊ダイヤモンドでエネルギー業界を担当。2016年ソーシャル型オンライン経済メディアのNewsPicksに参画、19年から現職。著書に、『アップル帝国の正体』(共著、文芸春秋)、『グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす』(文春新書)など。(写真:佐々木龍)
欧米は気候変動対策を加速
――米国では昨年8月、気候変動対策とエネルギー安全保障の強化策を盛り込んだ大型法案「インフレ抑制法」が成立しましたが、その後の世論調査では、気候変動を懸念する人の割合が減少したとの報告もあります。ロシアの侵攻後の急激なインフレに苦しむ米国の生活者の脱炭素に対する意識は変化しているのでしょうか。
「ロシアの侵攻前からNewsPicksで気候変動問題の特集を企画していましたので、私もウクライナ戦争が脱炭素に逆風になるかと一時思いましたが、実際にはそうはならず、むしろ中長期的な意識は高まっていると感じています。もともと米国の半分は気候変動では日本に近いスタンスで、それほど高い関心を集める問題ではありませんでした。それがバイデン政権誕生後、コロナ禍の中で熱波の被害も重なり、関心が高まりました。今や米国の気候変動問題は対策を進めるという点では決着がつき、どのように急進的に進めるのかに議論の中心が移っています。生活者にとってはロシアの侵攻後に急速に進んだインフレが大きな問題で、気候変動は一番の関心事ではなくなったかもしれませんが、多くの人が当たり前の問題意識として捉えていると思います」
――森川さんはロシアの侵攻後に脱炭素の動きを欧州で取材し、番組配信していますが、欧州の人々はどうでしたか。
「欧州でも特にドイツは地理的にウクライナとの間にポーランドしかなく、ウクライナ難民も身近にいて、ウクライナ戦争を自分事と受け止めている感じが強いです。足もとでは天然ガスを減らして石炭を使うなど脱炭素に逆行していても、中長期については『プーチン許すまじ』との思いが国民全体に染み渡っていると感じました。この冬は暖冬傾向で何とか乗り切れそうなこともあり、今後についてはロシアの天然ガス、石油からの脱却を国民が高いレベルで共有している印象です。では、再生可能エネルギーですべて賄えるのかというと、専門家では意見が分かれつつも世論は肯定に傾いています。原子力の利用では、ドイツは後ろ向きな人が多いものの、欧州のほかの国では、ロシアの化石燃料に頼らないエネルギー調達・経済の構築と脱炭素を両立するためには原子力を活用するべきという意見が多くなっています。エネルギー分野以外でも脱炭素でやっていくという意志は、さまざまな企業のすみずみにまで行き渡っていると感じました」
――深刻なエネルギー危機の中でも欧州が脱炭素への強い意志を示し続ける背景には、何があるのでしょうか。
「ロシアや中東と地理的な距離が近いという地政学的リスクと、歴史的な気候変動自体のインパクトがあると思います。戦争が遠くの国で起きているのと、近くで起きているのとは大きな違いがあります。石油が富の源泉となって約100年。彼らは長い歴史を生き延びてきて、次のエネルギーの時代も自分たちが覇権を握るとの強い思いとともに、気候変動によって被害を受けるのは自分たちではないのかとの思いもあります。気候変動が原因ともいわれるゲルマン民族の大移動などの歴史を含めて、欧州の人たちと話していると、きれい事の部分もありますが、気候が変動すると自分たちの社会に大きな影響が出ることを肌感覚で知っているのかなと感じることがよくありました」
高まるイノベーションの熱気
――日本も2050年のカーボンニュートラル(CN、温室効果ガスの排出量実質ゼロ)を表明しましたが、欧米からは周回遅れといわれています。
「今米国で起きていることは、従来は環境保護関連の人たちの取り組みだったCNが、明らかにビジネス側の人たちに伝播しているということです。脱炭素を成長戦略やイノベーションにつなげていく考え方で、そこには省エネ、節電など我慢の発想は少なく、エナジーアバンダンス(豊富な電力)という言葉が流行しています。脱炭素電源である再エネや原子力、さらに将来は核融合で大量の電力を生み出せば、エネルギー利用を電化し、これまで以上に電気を大量消費する時代になるという考え方です。気候変動対策のために電気を使うのを我慢するという人より、脱炭素をビジネスチャンスとして捉えている人が明らかに増えているのが日本との一番の違いかなと感じています。もともと日本はハイブリッド車をはじめ省エネ技術を得意とし、実際にCO2を減らしてきました。しかし、今起きていることは我慢して少しずつ減らすのではなく、ネットゼロですから、ゼロのイノベーションに進まないといけません。省エネでは米国は日本とは比べものにならないほどルーズですが、全部を再エネなどの脱炭素電源にしてしまえば、CO2を出さないエネルギーに書き換えられるというパラダイムシフト(価値観の劇的変化)的発想で、CO2ゼロのエネルギーを作りまくれとなっています。国が力を入れるとなったとき、一気にその方向を向いて突き進む力強さを感じさせるものが米国にはあります」
――欧米には日本にない脱炭素への熱気があるということですか。
「米マイクロソフトは、日本では聞きなれない『カーボンネガティブ』を30年に実現することを目標にしています。これはCO2排出量より削減量を大きくすることで、50年には1975年の創業時からの排出量をすべて相殺し、ゼロにする計画です。どうしても削除できないCO2は、大気中のCO2を直接回収し、さらに地下に半永久的に貯蔵するダイレクトエアキャプチャー(DAC)という技術が注目されています。実際、DACに取り組む企業が数多く出てきて、一部のIT企業が数千億円単位で投資するなど、この1、2年でものすごい勢いで資金が集まっています。マイクロソフトもDACに出資しており、自社のネガティブ実現の先にある排出権ビジネスも見据えているわけです。スイスの環境技術開発ベンチャーのクライムワークスがアイスランドで事業化するDACを昨年春に取材しましたが、その後資金が増えて9倍規模のプラント=イメージ写真(クライムワークス提供)=を建設しているといいます。CO2直接回収ビジネスの熱気はものすごいことになっています。大量の脱炭素電力を生み出す次世代技術として核融合も注目されており、多くの資金が集まっています。もう一つ、日本では当たり前にエアコンなどに使われているヒートポンプ技術がEU(欧州連合)では空気熱などを活用する再エネ利用技術と認識されています。ガスを使わずに少ない電気で暖房できるため、ドイツではすごい勢いでヒートポンプ式エアコンの導入が進んでいます」
――日本が脱炭素で巻き返すために必要なことは。
「日本でCNが我慢や犠牲を伴う義務のように受け止められているのは、CN後を見据えた社会のビジョンが示されていないためではないでしょうか。日本にしかできないイノベーションを打ち出し、新たな希望を示していくことが重要だと思います。日本にも、火力発電最大手のJERA(ジェラ)が開発しているアンモニア火力のような独自技術はあります。しかし、かつて再エネの強者だった日本のプレゼンスを世界に見せられるイノベーションももっとあっていいはずです。原子力にしても、当面の電力需給と脱炭素の両立やエネルギー安全保障では、大事な役割を果たすと思いますが、いつまでも旧型の既存原子力発電所を稼働させるのではなく、次世代に向けた研究開発が重要です。ドイツの取材では、2000年代に世界の携帯電話市場を制し、アイフォーンの登場によって一瞬にして事業売却に追い込まれたフィンランドの通信インフラ企業のノキアを例に出して、『時代の変化の先では、強者もあっけなく倒れてしまう』との声を多く聞きました。一方で、先ほどのヒートポンプにしても、まだ気づいていない日本の技術の強みもあり、脱炭素で遅れていると卑下する必要はないとも感じます。巨額の資金を投じてイノベーションに乗り出す政府方針も出ています。後はCNでCO2排出をゼロにする目標だけでなく、イノベーションによるCNの先にある未来社会を示す『ビッグピクチャー』を描いて、進んで欲しいと思っています」
(次回掲載は3月3日)