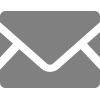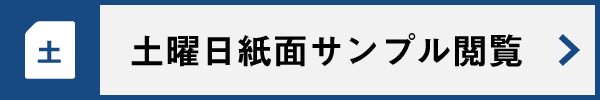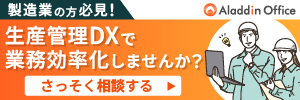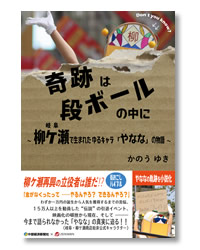再エネと原子力で脱炭素と自給率向上を
ピクテ・ジャパン シニア・フェロー 市川 眞一さん

いちかわ・しんいち 1963年東京都生まれ。87年明治大学卒。日系証券系投信会社のファンドマネージャーなどを経て、94年以降、フランス系、スイス系2つの証券会社にてストラテジスト。2019年9月から現職。内閣府規制・制度改革委員会委員、行政刷新会議事業仕分け評価者など公職を多数歴任。テレビ東京ワールドビジネスサテライトのコメンテーター。著書に『政策論争のデタラメ』(新潮新書)、『あなたはアベノミクスで幸せになれるか?』(日本経済新聞出版社)など。
欧州で高まる原発の重要性
――ロシアのウクライナ侵攻の影響でロシアへのエネルギー依存度が高かったEU(欧州連合)は深刻なエネルギー危機に直面し、不安が高まっているといわれます。EUのエネルギー危機はどのような状況なのでしょうか。
「欧州におけるエネルギーのロシア依存度は天然ガスで約40%、原油で約20%と高く、特にドイツは天然ガスの約55%をロシアから調達していました。ロシアの侵攻後、EUは2027年までにロシアからのエネルギー輸入を全面的に停止する方針を決めています。一方、ロシアはEUによる制裁の対抗措置として、主要なパイプラインである『ノルドストリーム』を停止するなど、天然ガス供給を大幅に削減しました。EU各国は天然ガスの貯蔵を増やしていますが、天然ガス価格の急騰による電気・ガス料金の大幅値上げでインフレ圧力が高まり、国民生活が圧迫され、この冬を乗り切れるのかという不安に直面しています。そうした中、私は昨年10月下旬から11月上旬にかけ、イタリア、スイス、英国を訪問しました。最も知りたかったのは、深刻なエネルギー危機下、ESG(環境、社会、企業統治)を重視する投資に積極的に取り組んできた欧州の姿勢に変化があるのか否かです。結果としては、ロシア侵攻後も欧州のESG重視の方向に変化はないとの印象を強く受けました。その根底にあるのは、エネルギーの自立でしょう。『化石燃料の多くをロシアに依存していたゆえに、ウクライナ戦争によって欧州経済は危機的状況に追い込まれた。これを克服するにはエネルギー自給率を向上させる以外に方法はない』という賢い判断です。今冬は奇しくも暖冬が味方してくれているとはいえ、中長期的に脱炭素電源である再生可能エネルギーと原子力を組み合わせることで、将来に向けエネルギー自給率の向上と地球温暖化抑止の両立によって危機を乗り切る明確な方針を固めていると感じました」
――原子力については、国による温度差がありませんか。
「国のエネルギー事情によって再エネと原子力の組み合わせ方が異なるのは当然だと思います。ドイツの再エネ比率は40%を超えており、その努力と実行力は称賛しなければなりません。しかし、21年、22年と2年連続の異常気象で十分な風が吹かなかったことから、ドイツとスペインでは電力供給が不安定化し、昨年夏に電力危機を招く一因となりました。将来的には大型蓄電池に再エネで発電した電気を蓄えるなどの対策が考えられるものの、現在はそこまで蓄電の技術が至っていません。従って、再エネを活用するにあたり合理的なコストで常時安定的に発電できるベースロード電源の確保が重要なテーマなのです。EU全体としては昨年1月、脱炭素に貢献する投資対象に原子力を追加しました。この決定に反対していたドイツも、昨年末での運転停止を予定していた原子力発電所3基について、稼働を23年4月半ばまで延長することを決めています。EUは天然ガスも選択肢としていましたが、最大の調達先であったロシアの問題によって原子力の重要性は以前より高まっているでしょう」
――日本でも今、電力の供給不安が問題となり、電気料金も上がっています。
「私たち日本人は非常に幸運なことに電気と水は当たり前に使える生活に親しんできました。東日本大震災後に計画停電もありましたが、一般電気事業者(大手電力)が供給義務を負う時代が続いていたため、震災後に原発が停止しても、際どい状況の下で電力はおおむね滞ることなく供給されてきました。もっとも老朽化した火力発電所に依存して割高な燃料費を払い、何とか供給体制が維持されてきたことを、私たちは明確に理解する必要があるでしょう。ちなみに、国際的にみれば通常、燃料費の上昇分は電気料金に転嫁されます。日本の場合は全面自由化後の経過措置として家庭向けだと規制料金が残っているため、電力会社が負担する形で実質的に料金上昇が抑えられてきました。私たち国民にとっては幸せなことですが、危機感が共有されないため、エネルギーを取り巻く世界の状況が理解されにくいと言えるかもしれません」
燃料の輸入依存も円安要因
――エネルギー資源の輸入価格は、一時急速に進んだ円安も上昇圧力になっています。市川さんは円安要因として、日米金利差とともに日本が主要国で最も低いエネルギー自給率(約11%)であるという脆弱(ぜいじゃく)性をあげています。
「ロシア侵攻後の世界の主要通貨の動き(22年10月7日時点)をみると、エネルギー自給率が727%と突出して高いノルウェーの場合(数字が大き過ぎて左上のグラフには入れていない)、通貨であるクローネは対ドルで約10%上昇しました。自給率の高いカナダ、ブラジルの場合も、通貨の対ドル下落率が相対的に小さくなっています。一方、最も自給率の低い日本の円は一時1ドル=150円を下回り、下落率が30%を超える局面もありました。理由は非常に単純で、石油、天然ガスなどの燃料価格が上昇している中で円安となったため、掛け算で貿易収支が悪化したからです。日本のようにエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている国は、化石燃料価格の高騰が貿易収支の悪化を通じて通貨を下落させ、さらに貿易収支が悪化して通貨を下落させる負のスパイラルに陥りました。世界が新たな分断の時代を迎える中、エネルギー安全保障での脆弱性が、円の弱さの背景になった可能性は否定できないと考えています」
――政府は12月下旬、50年のカーボンニュートラル(CN、温室効果ガスの排出実質ゼロ)実現に向けて原子力の活用に一歩踏み込んだGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議の基本方針案をまとめました。
「原子力は準国産エネルギーですから自給率を高める点でも評価できます。国際情勢が不安定化している中で、欧州のみならずどの国・地域にとってもエネルギー自給率をいかに高めるかが重要な課題になりました。日本において自給率向上とCNの両立を考えた場合、主要な解の1つは再エネの拡大でしょう。もっとも再エネの場合、主力の太陽光、風力は不安定な電源ですから、ベースロード電源が必要になります。例えば、電気自動車を走らせるためには夜間に安定的に大量の電気を生み出す脱炭素電源が不可欠です。そうなると、現実的な判断としては再エネと原子力の組み合わせが最適であり、その先に水素・アンモニアの活用を視野に入れなければなりません。申し上げるまでもなく、福島第一原発の重大事故があり、今も大変なご苦労をされている方が数多くおられます。その反省の下で行政においては安全性を審査する独立機関として原子力規制委員会が設置されました。そうした前提の上で、安全性が確認された原発の再稼働は極めて現実的な選択です。さらに、GX実行会議は『次世代革新炉の開発・建設の検討』にも踏み込みました。廃炉となった原子炉を安全性を高めた次世代炉にリプレース(建て替え)する方針ですが、厳しい国際情勢にかんがみれば、この政府の原子力政策は評価して良いと思います」
――日本の安全保障環境が一段と厳しさを増している中で、経済安全保障の観点からエネルギー政策の重要性は高まっています。
「経済安全保障は国を守る第一歩であり、今の世界の共通概念になりつつあると言えるでしょう。エネルギーは経済安保の要であり、安保で一番重要なことは弱みを見せないことです。5年ほど前だったと記憶していますが、中国人民解放軍海軍の幹部が『LNG(液化天然ガス)船の運航を阻害することによって2週間程度で日本経済を麻痺させることができる』とする論文を発表しました。今日本のエネルギー自給率が低い中で、国際情勢がこれだけ先鋭化してくると、何かをきっかけに化石燃料の調達が一時的にせよ困難になる可能性があります。それに対し、どのような防衛措置を持っているかが問われるでしょう。例えば、LNGの輸入を止められても、日本は再エネ、原子力を持ち、ある程度自立しているとなれば、LNG船を止める意味自体がなくなります。当面は再エネと原子力を組み合わせたうえで、水素・アンモニア利用技術やCO2の回収利用・封入技術、バックアップ電源としての大型蓄電地の開発を総合的に進めていくことが重要ではないでしょうか」