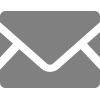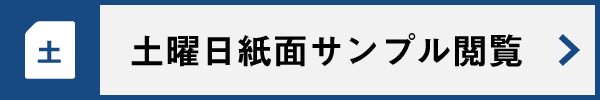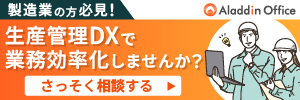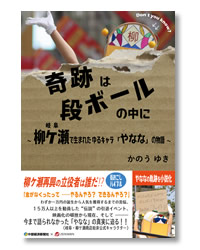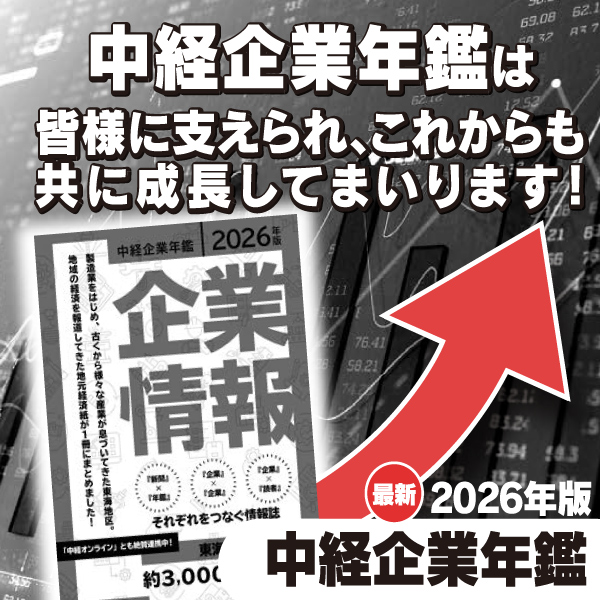あいち女性輝きカンパニー特集
理念から実践へ改正法が促す女性活躍の次なるステージ
法整備の背景
2015年に女性活躍推進法が成立された背景には、少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、社会の持続的な成長を可能にする多様な人材の活用という課題があった。当時すでに男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などの法的枠組みは存在していたが、依然として日本の管理職に占める女性比率は国際的に見ても低く、賃金格差も顕著なままだった。そうした状況を是正し、女性が能力を十分に発揮できる職場環境を整えるために女性活躍推進法は時限立法として制定された。企業に対し行動計画の策定と情報公表を義務づけ、現状を「見える化」することによって、意識改革と具体的な取り組みを促進するのが狙いだ。
施行から一定の期間を経て、改善の兆しはみられたものの、実効性という点では限界が指摘されていた。たとえば企業ごとの情報開示にばらつきがあり、男女間賃金格差の実態は社会全体に十分に共有されていなかった。

企業意識と改正点
実際のところ、企業意識はどうか。愛知県の調査では「女性の活躍推進を重視している」または「やや重視している」と回答した企業は全体の74.8%に上り、女性活躍を重視する姿勢が社会に広く浸透しつつあることが分かる。一方で、具体的に取り組んでいると答えた企業は41.8%にとどまっており、理念と実践の間には依然として隔たりがある。
こうした課題を踏まえ、今年6月11日に女性活躍推進法の改正法が公布された。改正点は主に次の三つだ。
まず有効期限の延長。もともと26年3月31日までとされていた期限を、36年3月31日まで10年間延長した。これにより企業は一過性の取り組みではなく、中長期的な視点で取り組めるようになる。
二つ目は、情報公表の必須項目拡大だ。これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金格差について、101人以上の企業に公表義務付けを拡大。また、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務づける。従業員や求職者が企業を選ぶ際に参考となる情報が整備されるとともに、各社の取り組みの進展が可視化され、結果として競争的に改善が進む効果が期待される。
そして三つ目は、「プラチナえるぼし」認定の要件追加。プラチナえるぼしは、女性活躍推進に積極的な企業を評価する制度の最上位区分で、その認定要件にセクシュアルハラスメント防止に係る措置内容の公表が加わる。
今回の改正は、女性が働きやすく活躍できる環境づくりを一層後押しするものであり、多様な人材が能力を発揮できる社会の実現に向けて、さらなる前進につながることが期待される。